日曜日は尼崎にて「みんなのサマーセミナー」、センセイとして参加してきました☆
僕にしては珍しく「喫茶店から考える、公と個の役割」なーんて真面目ぶったタイトルで50分喋ってきたんだけど。
いつかは非常勤講師とか講義してみてーな!と思っていたので、練習がてらやってみたら、これがなかなか難しい!!
テンポとか間の取り方とか、声の大きさとか喋る早さとか、抑揚とかコミュニケーションとか。
自分で映像見ながらダメ出ししながら(笑)
やっぱりプロの世界はキビシーですよね、何事も。
もーこれも場数踏むしかないですよねぇ。
[kad_youtube url=”https://youtu.be/9uvh8X5BPJI” ]
自分で授業しながら、話しながら、いくつか気付いたこともあってね。
例えば、「働くってなに??」って聞くと、だいたい「お金を貰うこと」ってなると思うんですよ。
仕事や職業などもそれにあたるのかな。
でも、お金がなかった時代や、お金があまり流通していない地方の村では、働くことの対価として「お金を貰うこと」という理由が成立しにくくなるわけですよね。
お金自体の価値がその周辺においては低かったりするわけだし、1万円札の価値を1万円相当だという相互信用がなければ、貨幣は意味がありません。
じゃあ、江戸時代の農村の人達は働いていなかったのか?というと、やっぱり働いていたわけで。
自分たちで食べる分を作ったり、周りの人のためにも野菜を作ったり。魚と交換したり。
家を修理してもらった代わりに、ご飯を御馳走して、野菜を持って帰ってもらったり。
その他にも、子供たちの面倒をみんなでみたり、神社の手入れをみんなでしたり、文字を教えたり、歌を歌ったり。
洪水で橋が流された時に、若いのみんなで橋を直して、晩御飯を御馳走してもらったり。
自分たちの村をより住みやすく過ごしやすくするために、少しでもかたちが歪んだり、欠けてしまったり、負荷がかかった時に、その村人は「保全」という名のもとその部分に対して「働きかける」わけです。
つまり、「働くこと」というのは、みんなが望むかたちへの保全活動。
目の前で起こっていることに対して、何をどれだけ働きかけることができるかです。
みんなの望むかたちをまとめることができるか?
そのかたちを共有することができるか?
欠けている部分(保全シロ)を見せることができるか?
かたちを育み、ゆるやかに最適化することができるか?
その仕組みを委ねることができるか?
事業主としてもこれはけっこう大事な話で、これからも掘り下げて考えていこうと思いました。
まーでも今回の授業、生徒のみなさんにかなり保全されましたけどね(笑)
素敵な出会いもたくさんあり、すごく有意義な時間でした!
ありがとうございました☆

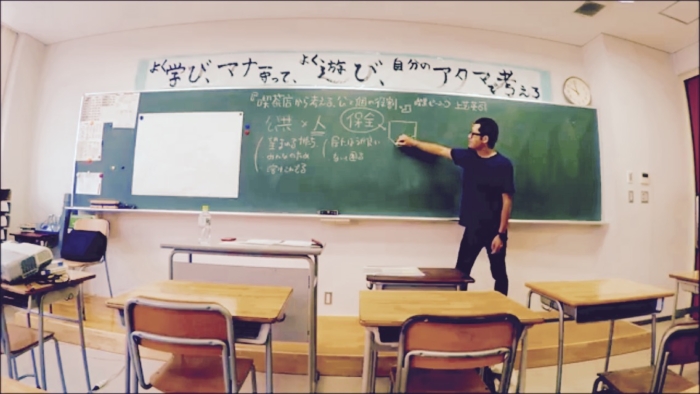




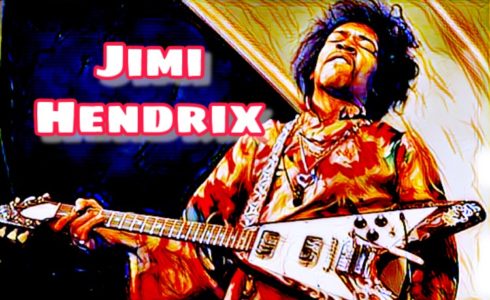
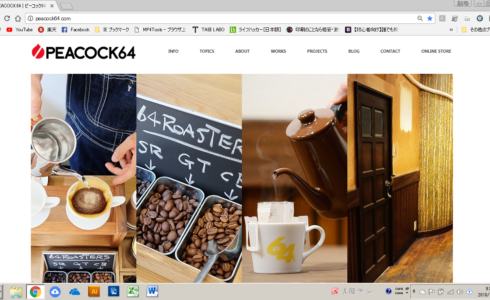








この記事へのコメントはありません。